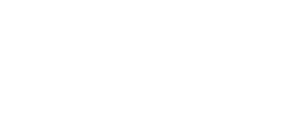大歌人が留学先で楽しんだ鯉料理と本場のドイツビール
精神科医でありながら、歌人としても優れた歌を残したことで知られる斎藤茂吉は、1882(明治15)年、山形県に生まれた。14歳のとき、同郷の医師・斎藤紀一に目をかけられて上京。のちにその養子となり、紀一の次女を妻に迎えた。東京帝国大学医科大学(現在の東京大学医学部)を卒業して医師免許を取得する一方、1913(大正2)年に第一詩集『赤光(しゃっこう)』を刊行するなど、アララギ派の代表的歌人として活躍した。
茂吉が、最もビールに親しむ機会を得たのはおそらく、1923(大正12)年から1年あまり滞在したドイツのミュンヘンでのことであろう。1921(大正10)年、すでに歌人としては一定の評価を受けていた茂吉は、もう一方の専門である医学の研究のため、オーストリアのウィーンに留学した。さらに2年後、ミュンヘン大学のドイツ精神病学研究所に転学するのである。
1926(大正15)年に発表された随筆『ドナウ源流行』は、このミュンヘン滞在中に茂吉が楽しんだ、ドナウ源流を訪ねる旅の体験を描いたものだが、この中にも、ドイツ南部のドナウ河畔の街ウルムで、鯉料理を食べ、ビールを飲んで「秘かに幸福を感じ」た、というエピソードが描かれている。
また、茂吉の次男で作家の北杜夫が、斎藤家の人々をモデルに描いた『楡家の人びと』にも、ビールが登場する印象的なシーンがある。茂吉をモデルとする「楡徹吉」はミュンヘン留学中、新聞で関東大震災のニュースを知る。そのとき、ビールを飲んでいた徹吉は、あまりの衝撃に現実感を抱けないままに、ビールのお代わりを頼んで「一息にぐっと半分ほど」干すのである。もちろんそれがそのまま茂吉自身の行動であったとは限らないが、ビールの本場で、茂吉がうれしいにつけ悲しいにつけ、ビールのグラスを傾けていたであろうことは想像に難くない。
1924(大正13)年に帰国した茂吉は、父親が設立した青山脳病院の院長となり、医師として忙しい日々を送る一方、歌人としても精力的な活動を続けた。70歳で亡くなるまで、詠んだ歌は1万5,000首以上にものぼるという。