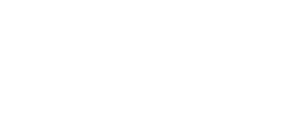洋酒との邂逅
1846(弘化3)年、浦賀奉行配下であった下岡蓮杖は、浦賀近くの野比村(現在の横須賀市野比)沖に停泊した軍艦に座乗する、アメリカ海軍の東インド艦隊司令長官ジェームズ・ビッドルに面会した。その際、ビッドルの命で蓮杖のコップにボーイが注いだものは、「眞赤な生血(なまち)」のような液体。これを出された蓮杖は度肝を抜かれ、毒が混ぜてあると思いながらも、この身を日本国のために捧げようと決心、目を閉じて一息に飲み干したという。だが、その液体を飲むと「精神も何となく開けて来た」「甘露のやうに甘かった」……。のちに画家であり写真家、実業家となった下岡蓮杖が、ワインをはじめて飲んだときの記録である(『横濱開港側面史』横濱貿易新報社、1909年刊)。
時代が江戸時代後期から幕末になると、開国により、様々な外国文化が流入した。ワインなどの洋酒も、それ以前からわずかながらも日本に持ち込まれてはいたが、この頃から本格的に輸入が開始される。
その理由は、1858(安政5)年に結ばれた日米修好通商条約をはじめとした諸条約により、開港した地には外国人居留地が設けられたからだ。そこには外国人、家族を同伴した日本駐屯軍の外国兵が年々増加。これに目をつけた居留地内の商社が関税の減免制を利用して洋酒を輸入、販売を開始したのである。長崎では1860(万延元)年にアーノルド商会が、横浜では1861(文久元)年にO.H.ベーカー商会が、それぞれワイン、シャンパンなどを売り出している。
だが、輸入量は増えても、日本人には洋酒はなかなか浸透しなかった。高価なこともその一因だが、欧米においてワインは「キリストの血」とされているものの、そうした背景のない当時の大多数の日本人にとってはあまり興味をひくものでなかったのである。この傾向は明治20年代、ワインが健康保持のための飲料として宣伝、認知されるまで続くことになる。
「横浜異人商館座敷之図」
横浜や長崎に居留した外国人たちを中心にワインやシャンパンなどの洋酒が飲まれていた。(神奈川県立歴史博物館提供)
世界に羽ばたく日本茶
茶の海外輸出の先駆けと言われる長崎商人・大浦慶。アメリカへの茶輸出は1861(文久元)年からの南北戦争によって一時的に減少したが、その後ますます人気が高まり輸出量も増加していった。(長崎歴史文化博物館 提供)
一方、海外からもたらされるものもあれば、逆に日本文化が海外でもてはやされることもあった。その代表格が日本茶である。
戦国時代以前は高価で庶民には手が届きにくかったお茶は、江戸時代に入り、生産量が大きく拡大したことから人々の生活の中に組み込まれ、特に煎茶は庶民でも楽しめるものとなっていった。しかし、生産量が増えたとはいえ、産業としてはごく小規模。まだ、茶の湯など芸術文化の側面も色濃く残していた。
それが変わったのは幕末以降。開国して世界経済の中に組み込まれた当時の日本には、これといった輸出産品がなかった。そこで重要な輸出品目となったのが生糸と茶であったのだ。
茶の海外輸出は1853(嘉永6)年、長崎の商人であった大浦慶に始まるといわれる。慶は長崎商人の娘として生まれるが、実家は火事で没落。その再興のため、オランダ人商人に頼み、イギリス、アメリカ、アラビアに茶のサンプルを送付した。その後、1856(安政3)年にイギリス商人から大量の注文を受け、アメリカに輸出。これが先駆けとなり、日本茶の持つ可能性が世に知らしめられた。
ちなみに、日本に開国を促すために来日したアメリカのペリー提督が、横浜で幕府役人の接待を受けた際に特に好んだのが煎茶であったというエピソードも残されている。
こうして明治維新、文明開化を迎える準備が、飲料においても着実に進んでいったのである。
輸出する茶を納めた茶箱には、蘭字(「西洋の文字」の意味)が書かれたラベルが貼られていた。ラベルは薄い和紙でできており、茶箱は梱包材で
包まれ出荷されていた。このラベルは1903(明治36)年のもの。
(四日市印刷工業株式会社 提供)