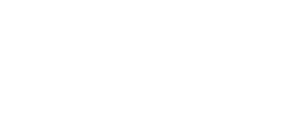「(ビールを)一杯ぐつとのむとそれが食道を通るころ、丁度ヨツトの白い帆を見た時のやうな、いつでも初めて気のついたやうな、ちよつと驚きに似た快味をおぼえる。麦の芳香がその時嗅覚の後ろからぱあつと来てすぐ消える。すぐ消えるところが不可言の妙味だ」(「ビールの味」)
ビールの芳醇な香りとすっきりしたのどごしを見事に描写したこの記述は、詩人であり芸術家の高村光太郎が、1936(昭和11)年に随筆「ビールの味」に記した一節だ。彼は自他ともに認める酒好きであり、ビールに関する文学的な記述を多く残している。
1883(明治16)年、彫刻家・高村光雲の長男として生まれた光太郎は、父と同じ彫刻の道を歩むと同時に、評論家、詩人、画家など多彩な顔を持つ。妻への想いを綴った詩集『智恵子抄』が舞台や映画化もされ知名度を得たことから、詩人として認識されることが多い。
光太郎は彫刻を学ぶために20代前半に世界へ飛び出し、ニューヨーク、ロンドン、パリと数年間放浪した。1909(明治42)年に帰国するが、先進都市の空気を体感した光太郎にとって、日本の芸術界はひどく保守的に映ったようだ。東京美術学校の教職という安定した地位を手放し、評論「緑色の太陽」を執筆して芸術の自由を宣言。そののちは1956(昭和31)年に73歳で死去するまで、前衛的な創作活動に邁進し続けた。
ビールの味は、この若き日の欧米留学中に覚えたようだ。「ビールの味」の中にも「ロンドンでバスといふビールのひどくうまかつたことを記憶している」と書いている。さらに「ビールの味」には次のような記述も見える。
「ビールの新鮮なものになるとまつたくうまい。麦の芳香がひどく洗練された微妙な仕方で匂つて来る。どこか野生でありながらまたひどくイキだ。さらさらしてゐてその癖人なつこい」(同上)