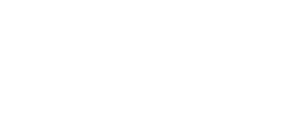ジンは「薬」であった
江戸時代後期のジンボトル。オランダ製で、ボトルにはオランダの会社名「I.T.BEUKERS SCHIEDAM」の文字が刻印されている(長崎市歴史民俗資料館 所蔵)
マティーニ、ジンバック、ジントニック、ジンライム……。日本ではカクテルのベースとして使われることの多いジン。この酒、実は薬として誕生したことをご存じであろうか。
もともとジンはオランダ生まれ。ライデン大学医学部のフランシスクス・シルビウス教授によって1660年に製造されたとされる。当初は、医師によってつくられたことからも分かるように、マラリアやチフスといった熱病の治療薬として期待されていた。ジンの製造に用いられる杜松(ねず)の実は、利尿や解熱作用があると知られており、これを用いることで利尿・解熱薬として薬局で売り出されたのである。ところが、そのさわやかな香りから、薬としてではなく酒としてオランダ国内で流行。フランス語で杜松の実を意味する「ジュニエーブル」の名で広く親しまれた。その過程で、なぜかスイスのジュネーブと混同されて「ジェネバ」、さらにイギリスに渡ったときに、これが短縮されて「ジン」と呼ばれるようになったという。
イギリスに渡ったジンは、本国以上に爆発的な人気を得る。その頃のイギリスでは質の悪い酒が多かったことに加え、オランダから迎えられた当時の国王・ウィリアム三世がジンを優遇し、関税を安くしたことなどによる。このほか、原料の穀類が豊作続きで安かったこともあり、瞬く間に「安くて強い酒」として労働者階級に広まったのである。
輸入洋酒の草分け的存在
一方、日本にジンが入ってきたのは、いつのことだろうか。はっきりとした記録はないが、江戸時代には伝来していたことが確認されている。というのも鎖国時代、長崎の出島で働いていた日本人の中には、そこに住む外国人たちが飲んでいた酒のボトルを持ち帰る人がいたが、その初期のものの中にジンのボトルも含まれていたのである。これらのボトルは、観賞用や保存容器、また溶かして新たなガラス製品をつくるなど、さまざまな使い方をされたという。
とはいえ、ジン自体を一般庶民が口にできるようになったのは明治以降のこと。1870(明治3)年に横浜の外国人居留区にあったカルノー商会がジンを輸入・販売したという記録が残っている。もっとも、いまのように気軽に洋酒が飲める時代ではなく、一部の人々が楽しむ嗜好品ではあった。それでも確実にジンはわが国の文化に溶け込んでいき、カクテルのベースとして使われるようになる。特に「ミリオン・ダラー」というジンベースのカクテルは、明治時代に横浜のホテルで考案され世界に広まったもの。このように、世界で愛される日本発のジンのカクテルまで生まれている。
カクテル「ミリオン・ダラー」が誕生した、横浜グランドホテル。1870年、英国公使館跡地に開業し、のちに横浜を代表するホテルとなったが、関東大震災で焼失。1927年に解散した(横浜開港資料館 提供)
ジンがなければサワーやチューハイはなかった!?
オランダからイギリスに渡ったジン。実は、イギリスにジンが伝来したことが、現在の日本の酒文化に大きな影響を及ぼしている。それは、ジンと日本の焼酎とが結びつく深い縁があるからだ。
ジンも焼酎も蒸留酒であり、原料をアルコール発酵させたものを蒸留してつくるのだが、蒸留の仕方には二通りの方法がある。
1回だけ蒸留する単式蒸留では、原料の香りや味わいがはっきりするが、酒精(酒の主成分であるエタノール)の精製度は低くなる。この方法でできた焼酎は「焼酎乙類」と分類され、麦・米・いもなどの原料の風味を生かした味わいが特徴である。一方、複数回蒸留する連続式蒸留の場合は、酒精の精製度が高くなる。この方法でできた焼酎は、「焼酎甲類」と分類され、純粋で洗練された酒質が特徴である。サワーやチューハイにはこちらが用いられることが多い。
さて、この焼酎甲類は、1910(明治43)年に愛媛県の日本酒精株式会社が発売した「日の本焼酎」が最初であった。当時、「ハイカラ焼酎」と呼ばれ、安くて品質がよいため好評を博した。「日の本焼酎」は当時最新式の連続式蒸留器によって製造されたが、この機械は1830年代にイギリスで開発された後、改良が重ねられ、1895(明治28)年頃から日本に輸入されていた。その最新式の機械を用いた焼酎であることから、「ハイカラ」と称されたのである。
実は、この連続式蒸留器は、もともとイギリスでジンをつくるために開発された。つまり、イギリスにジンが伝来せず、ジンを製造するための技術が生まれなければ、日本の焼酎甲類は生まれなかったかもしれない。焼酎甲類を使うことが多いチューハイやサワーも、現在のように広く飲まれていなかったかもしれないのだ。
ジンは日本の酒文化にとって、間接的ながら多大な貢献をした酒なのである。