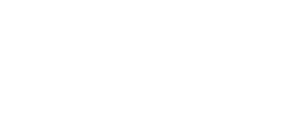輸出品として開発され、富裕層に愛された紅茶
輸出製品としての紅茶開発を急ぐ明治政府の要請を受け、中国やインドに派遣された茶業研究家の多田元吉。茶樹の品質改良や器具の考案など、緑茶や紅茶の生産・研究に大きな貢献をした。(静岡県茶文化振興協会 提供)
近年はティーバッグやペットボトル入りのものが販売され、馴染みの深い紅茶。しかし、当初は外国向けの輸出品としての色合いが強いものであった。
1859(安政6)年の横浜港開港以降、明治政府は茶を輸出事業の柱としていたが、やがてアメリカの市場では、緑茶よりも紅茶の人気が高まっていった。これを受け、政府は国内での紅茶生産と輸出産業化を開始する。
1874(明治7)年には内務卿・大久保利通の命で『紅茶製法書』を配布して生産を奨励する一方、清国の湖北地方やインドのアッサム、ダージリンなど、各国の著名な産地に技術者を派遣。先進の栽培・製造法を学び、機器や種子を持ち帰ると、日本各地に官営の紅茶製造技術伝習所が設けられた。同じ頃に静岡や三重、高知などでは、民間の紅茶会社による生産も始まっている。
イギリスやアメリカの商館を通して輸出され、質・量ともに高まっていった国産紅茶だが、国内では、あくまで一部の層の嗜好品に留まっていた。長年親しまれてきた緑茶文化が根強く、また紅茶は高価であったこともあり、鹿鳴館でのパーティーでハイカラ好みの上流階級に飲まれるような高級品であった。こうした状態は、大正時代末まで続いた。
文明開化の象徴としてのビール
紅茶と同じく、ビールもこうした社交場で盛んに飲まれていた。文明開化とともに日本人の生活様式が洋風化すると、食文化も西洋のものが広く持ち込まれた。その代表例がビールである。
当初は主に国外からの輸入品に頼っていたが、居留外国人らを中心として国内での需要が高まると、1870(明治3)年にはノルウェー出身のアメリカ人ウィリアム・コープランドが「スプリングバレー・ブルワリー」を創設するなど、国内での醸造が盛んになっていく。1885(明治18)年には、スプリングバレー・ブルワリーの土地を引き継いで、キリンビールの前身である新会社「ジャパン・ブルワリー・カンパニー」が誕生している。
1872(明治5)年には大阪の商人・渋谷(しぶたに)庄三郎が「渋谷ビール」を発売するなど、日本人によるビールの醸造も始まった。政府も殖産興業政策としてビール醸造事業に取り組んでおり、1876(明治9)年には、札幌に官営の醸造所(開拓使麦酒醸造所)が建てられている。
こうして、居留外国人だけでなく、日本人にも少しずつビールが飲まれるようになっていく。
当時、一般の人々がビールを飲める場所といえば、横浜や東京を中心に増えていた牛鍋屋や西洋料理店である。明治時代初期には、国産びんビール一本が米3〜4kgと同じ17〜20銭(1878年)と、庶民には手の出ない高級品であったが、やがて一杯5〜10銭という価格で樽ビールのコップ売りがされるようになった。消費量は急速に増加し、1883(明治16)年には約3,655石(現在の大びん換算で約104万本)であった国内消費量は、その後4年間で約26,561石(同 約755万本)にまで伸びている。大手ビール会社の設立が相次ぎ、1900(明治33年)までに建てられた国内のビール醸造所は100を超える程であったという。
当初、豊かさの象徴として楽しまれていたビールは、やがて手軽に楽しめる嗜好品として人々の食生活に根付いていった。
仮名垣魯文著『牛店雑談安愚楽鍋(うしやざつだんあぐらなべ)』に描かれた牛鍋屋の挿絵。「ビイル十八匁」と書かれた品書きが貼ってある(河鍋暁斎画)。