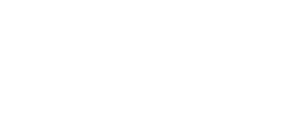ワインの伝来は戦国時代
神谷伝兵衛が発売した蜂印香竄葡萄酒(オエノングループ 合同酒精株式会社 提供)。
「香竄」は伝兵衛の父親の雅号であり、「竄」には香りが染み込むとの意味がある。
いまや日本人の食生活に欠かせないものとなったワイン。イギリスの調査会社・IWSR社によると、2011(平成23)年の日本人一人当たりの年間ワイン消費量は2.4リットル。1995(平成7)年には1.15リットルだったことを考えると、着実に伸びている。これは世界で19番目の消費量で、日本のワイン輸入量がアジアの中でトップなのもうなずける。そのうえ、外国産だけではなく、日本産のブドウを使い、品質のよいワインをつくろうという努力も続けられている。まだまだヨーロッパには及ばないまでも、まさにワインは日本人の日常に定着したといってもよいだろう。
とはいえ、ご存じの通り、ワインはもともと西洋文化の象徴で、日本には馴染みの少ないもの。では、そのワインが、わが国でどのような経緯を経て、現在の地位を確立したのか。その歴史を追ってみたい。
ワインにまつわる文献では、1466(文正元)年の京都の相国寺鹿苑院内蔭凉軒主(臨済宗と室町将軍とのパイプ役)の記録『蔭凉軒日録』には「南蛮酒を飲んだ」と書かれており、これがワインのことだと考えられている。さらに時は進み、来日したイエズス会の宣教師、フランシスコ・ザビエルは、本国から持参したワインを自身が布教を望む地域の大名に献上。また、豊臣秀吉も九州征伐で博多に立ち寄った際、ポルトガル船でワインを饗されたとされる。このように戦国時代を通してポルトガルなどからの輸入品として、ワインは徐々に浸透。一部の特権階級には飲まれるようになっていった。とはいえ数は少なく、ザビエルと同じイエズス会の宣教師、ルイス・フロイスは、著書『日本史』で日本ではワインが手に入らないことに閉口している。
日本のワインは甘かった?
その後、時を経て、わが国でワインの本格的醸造がはじまったのは明治時代。明治政府の殖産興業政策の一環として、ブドウ栽培、ワイン醸造が促進された。外国産ブドウの苗木を輸入し、東京の内藤新宿試験所と三田育種場で育成栽培が試みられた。さらに全国でブドウ栽培が奨励され、なかでも山梨と北海道で盛んだったが、特に山梨の人々の熱の入れようは他と一線を画した。すでに、江戸時代からブドウの名産地になっており、1874(明治7)年には、甲府の山田宥教と詫間憲久がワインを醸造。これが産業としての国産第一号のワインであった。しかし、事業は続かず失敗。すぐに廃業に追い込まれてしまった。
この二人を皮切りに、多くの人々がワイン醸造に取り組むが、この頃は、ほとんどが失敗の憂き目を見た。その理由としては、醸造技術が未熟であったことに加え、ワインに適したブドウの品種が日本の気候にあわなかったこと。さらには、焼き魚、味噌汁、ご飯を中心とした日本人の食生活に、タンニンの渋みがきいたワインは馴染まなかったことが挙げられる。
そこで考えられたのが、砂糖や酒精、香料などを加えた甘味ワインだった。1881(明治14)年に神谷伝兵衛が輸入ワインに蜂蜜と漢方薬を加えた「蜂印香竄葡萄酒」を発売したのをはじめ、「赤玉ポートワイン」などのヒット商品が続々誕生。昭和初期には、ワインを好きな庶民の数はかなりのものになっていた。
しかし、この甘味ワインは、思わぬ余波をもたらした。第二次世界大戦後、本格的な輸入ワインを販売しようとした事業者が、「ワインは甘いもの」と思い込んでいた人たちへの売り方に苦労したのである。それでも、日本人の食生活が大きく変わり、西洋風料理が日常の食卓に出るようになったことで、ワインはさらにメジャーになっていく。
東京オリンピックや大阪万博といった節目節目でワインは着実に消費量を伸ばし、1973(昭和48)年に前年対比1.6倍を記録。この年は、わが国ワイン業界で「ワイン元年」と記憶されるものとなった。さらに、1991(平成3)年のバブル経済崩壊以降、輸入ワイン価格が下落。それまでのワインは高価なものであるといった印象が変わり、品質のよいワインが手軽に買えるようになった。一方で、国内の醸造技術も飛躍的進歩を遂げ、日本の風土に適したブドウ栽培も可能になったことで、日本固有のブドウ品種で造った輸出専用商品も出来るなど世界からも日本のワインは注目されるまでになりつつある。ここに至り、ワインは完全に日本人の生活の中に溶け込んだのである。
現存する日本最古の木造ワイン醸造所・旧宮崎第二醸造所(山梨県甲州市、現・シャトー・メルシャン ワイン資料館)