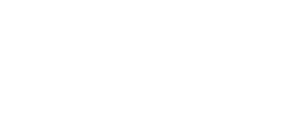(1)明治文学上のビールはハイカラな飲み物
歌集『一握の砂』などで知られる石川啄木(石川啄木記念館 蔵)
明治初期の文学は文体も形式も江戸時代までの近世文学とほとんど変わらないが、そこで描かれる風俗は当然明治のものであった。牛鍋店を舞台に文明開化期の人々を活写した仮名垣魯文(かながきろぶん)『牛店雑談安愚楽(あぐら)鍋』では、予告編で書生が「持参のビイル」を空にして、さらに店の酒を飲んでいる姿が描かれている。しかし、本編中、店内でビールを注文する客は皆無で、熱燗をきわめて熱くするように申し付ける客が多い。
明治中期から後期にかけて、言文一致による近代小説への転換が本格化していく。その時期はビール産業もまた大きく発展しつつある時期であった。尾崎紅葉の代表作『金色夜叉』(1897〜1902年)にも、ビールが登場する。お宮と別れて高利貸しになった主人公、貫一が旧友の家を借金回収のために訪問すると、旧友は「製造元から貰った黒麦酒」やハムなどで別の学友をもてなそうとしていたのだった。
当時、貫一の旧友のような一部の人々の間では進物としてビールを贈ることが始まっていた。明治末の夏目漱石『吾輩は猫である』(1905〜1906年)では、中学教師の苦沙弥先生が近所の金満家からビール1ダースを贈られている。しかしこの金満家を嫌う先生はビールを突き返した。一方、実業界に入った教え子、多々良三平から手土産にもらったビール4本は皆で飲み、その飲み残しをなめた猫は酔って水がめに落ちて死ぬ。なお、当時の「キリンビール」は一本23銭で、ざるそば一杯のほぼ10倍の価格であった。
値段は高くともビールはインテリに好まれ、学生の宴会でもビールを飲むことが少なくなかった。石川啄木は小説『雲は天才である』では「苦学生の口には甘露とも思はれるビールの馳走を受けた」と著している。
地方にもビールが普及し始めた様子は、田山花袋『田舎教師』(1909年)にも描かれている。主人公の小学校教員は、他の教員たちと埼玉県三田ヶ谷村(現・羽生市)の料理屋でビールを酌み交わしたり、船の渡し場近くの飲食店でビールを注文したりしている。
仮名垣魯文著『牛店雑談安愚楽鍋』に描かれた牛鍋屋の挿絵(河鍋暁斎画)。