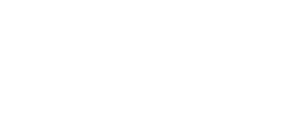(6)コルク栓から王冠栓へ
明治初期の国産ビールのびんにはコルク栓が使われており、栓が抜けないよう、針金でコルクとびんを固定していた。1888(明治21)年に発売された「キリンビール」には、大びんで1.75インチ(約4.4cm)、小びんで1.5インチ(約3.8cm)のスペイン製のコルクを使用していた。コルク栓を引き抜くのには手間がかかる上、抜いた瞬間に泡が吹き出すことも少なくなかった。
1875(明治8)年、アメリカで「機械栓」と呼ばれる針金つきの栓が開発された。機械栓は急速に世界に広まり、その2年後には日本にも機械栓の輸入ビールが入ってきた。同じ頃、国産ビール会社でも「日の丸ビール」がいち早く取り入れている。しかし、機械栓は価格がコルクよりも高く、洗浄に手間がかかるというマイナス面もあり、日本では結局普及には至らなかった。
その後も欧米の各国で栓の研究が進められ、1892(明治25)年、アメリカで使い捨ての新しい栓が開発された。開発者が形状から「クラウン・コルク」と呼んだ王冠栓である。炭酸飲料にも耐えられることから、英米を中心にサイダー、ビールなどのびんに採用され始めた。日本のビール会社では1900(明治33)年、東京麦酒が最初に採用した。しかし、多くのビール会社は採用をためらった。従来の吹いて成型するびんはびん口が不ぞろいで、王冠栓を取り付けるとガス漏れやびん割れが生じるためであった。
その後製びん技術が発達し、1907(明治40)年には、大日本麦酒が試験的に王冠栓付きビールを販売し始めた。麒麟麦酒では、ドイツ人技師が容器もドイツ製にこだわったため、採用はしばらく見送られ、代わりにコルクにアルミのカバーが付いた改良栓、「ゴルデーコルク」を1910(明治43)年に導入した。しかし、王冠栓ほど便利ではなく、2年後の1912(明治45)年に王冠栓を採用することにした。その後しばらくコルク栓、改良栓、王冠栓と3タイプの栓の「キリンビール」が流通したが、大正時代には王冠栓のみとなった。
日本で用いられた王冠栓は、はじめは輸入品だったが、1908(明治41)年、王冠栓の特許を持つイギリスの会社が横浜に工場をつくってからは、国産品で賄えるようになった。さらに日本での特許期限が切れた大正時代以降は、各地で日本人による王冠栓生産が始まった。以後王冠栓には、材質などでの改良が続けられている。
王冠のコルク抜き方法を描いた広告(「東京麦酒王冠栓導入広告」/アド・ミュージアム東京 蔵)