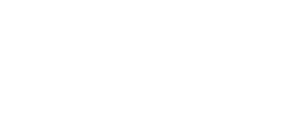(4)文壇全盛期のビール
1950年代から1960年代にかけては文壇がもっとも華やかだった時代である。酒好きの多い文壇の中でも酒好きでよく知られていたのは、政治家、吉田茂の息子としても有名な吉田健一だ。彼の優雅な飲食エッセイは、高度経済成長期の読者にとってはあこがれの世界であった。1955(昭和30)年刊行の『酒に呑まれた頭』収録のエッセイ「羽越路瓶子行」では、彼は食堂車のない列車に乗るため新橋の洋食屋、小川軒で折詰とビールを買い、グラスも店から借りている。※1「よくこういう場所に用いる紙のコップは、三本目のビールを注ぐ頃から溶け始めて、変にかみ臭いビールになる」というのが、グラス持参の理由である。当時はまだ缶ビールはなく、栓抜きも持参していた。
1950年代後半、文壇に好意的に迎え入れられたのが東大生、大江健三郎である。当時の風俗から国際情勢まで貪欲に取り込んだ長編小説『われらの時代』(1959年)では主人公の兄弟は「深夜喫茶」で再会し、戦争中に亡くなった両親の代わりに2人を育ててくれた伯父のためにビールで乾杯するのだった。
第二次世界大戦前は小説の読者は青年層が中心で、作家も30歳以下が多かったが、1960年代は読者も作家も年齢の幅が広くなる。大学で教えながら小説を書く、というタイプの作家も増えた。1970(昭和45)年に芥川賞を受賞して大学を辞めた古井由吉(よしきち)は、『妻隠(つまごみ)』(1970年)で、夫婦が駅前のスーパーマーケットの屋上で生ビールを飲む場面を描いている。夫婦の関係を描くことも当時の文学的風潮であった。
〈引用〉※1 吉田健一著 「羽越路瓶子行」 1955年刊行 筑摩書店