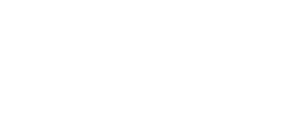ペリーの来航により日本が開国し、開港した横浜、神戸、函館などの居留地からは西洋の食文化が広まった。居留地には、外国人向けの西洋料理店が開かれるようになり、ビールは西洋料理の広がりとともに、日本人にも飲まれるようになった。
日本人が始めた最初の本格的な西洋料理店は、1863(文久3)年に長崎に開かれた「良林亭」といわれている。六畳一間の小さな店だったが、のちに洋館風に建てかえられ「自由亭」と名前を変えた。
最大の居留地であった横浜には、幕末に西洋料理と名乗る飲食店があちこちにできていたようだ。東京では、神田橋に1867(慶応3)年、東京初の西洋料理店「三河屋」が開業した。
西洋料理店はビールをはじめとする洋酒を提供した。東京の九段(現・千代田区富士見町)にあった西洋料理店
「南海亭」の明治初期の引札(チラシ)によると、店では1人前の料理として、スープ、フライ、ビフテキ、パン、コーヒーのセット、あるいはライスとシチューのセットを提供していた。洋酒はビールが大びん、小びん、グラスで提供されていたが、ビールの大びん・小びんの値段は、ビフテキのコース料理1人前よりも高かった。
明治の東京の代表的な西洋料理店である「精養軒」は1872(明治5)年にホテルとして開業し、外国人シェフによる本格的な料理が自慢だった。1876(明治9)年の上野公園の開設と同時に上野精養軒を開いて話題となり、柳橋の芸者4名が上野の精養軒で西洋料理を注文したところ、ビール1本をサービスとして提供されたことが新聞(『東京曙新聞』1876年4月20日付)で報道された。
明治20年代には東京の銀座、上野、有楽町、芝公園などの繁華街に、西洋料理店が相次いで開業し、西洋料理店の数も増えた。これらの店でビールを飲む人々も増えたが、高級西洋料理店の食事は高価すぎて、庶民には手の届かないものであった。
明治末の東京を舞台とする夏目漱石の小説『三四郎』では、主人公の三四郎が上野精養軒で開かれた会でビールを飲んでいるが、彼もはじめは会場の名前を聞いて出費が心配になり参加を渋ったさまが描かれている。