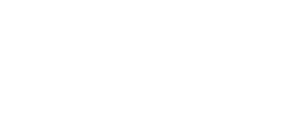大正に入るとカフェーが大流行し、「カフェー・ライオン」、
「カフェー・プランタン」、「タイガー」などが文学者のたまり場となる。カフェーの女給を描いた小説も数多い。また、この時代には稲垣足穂『一千一秒物語』(1923年)のような先駆的な作品も発表された。それに収められた掌編「はたしてビールびんの中に箒星がはいつてゐたか?」には、明治時代よりも味が軽く、炭酸が強くなった大正時代のビールが登場する。
昭和に入っても文学者はビールを好んだが、詩人たちはビールに対してもビールならではのポエジーを発見していた。たとえば中原中也はハイキングでビールを飲むという尖端的な遊びの中に、言い知れぬ悲しみを見た。「渓流(たにがわ)で冷やされたビールは、/青春のやうに悲しかつた。(略)ビョショビショに濡れて、とれさうになつてゐるレッテルも、/青春のやうに悲しかった」(1937年発表「渓流」より)。
一方、萩原朔太郎は大都会のビアホールで孤独を見つめた。「午後の三時。広漠とした広間(ホール)の中で、私はひとり麦酒(ビール)を飲んでた。(略)私は喪心者のやうに空を見ながら、自分の幸福に満足して、今日も昨日も、ひとりで閑雅な麦酒(ビール)を飲んでる。」(『散文詩』所収「虚無の歌」より)。このビアホールの詩は、「虚無よ!雲よ!人生よ」と締めくくられる。
詩人がビールに悲しみや虚無を見るようになった頃、戦争の影が日本を覆い始めていった。