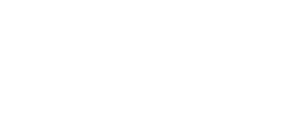大正時代から昭和前期にかけて、都市部への大規模な人口流入が起こり、都市文化が勃興した。そのきっかけとなったのが、1914(大正3)年に勃発した第一次世界大戦による特需である。ヨーロッパでは戦争が長期化するにつれて各種の物資が不足し、軍需品をはじめ工業製品の日本への注文が激増した。この特需で工業を中心に新たな労働力が必要となり、農村から都会への人口流入が進んだ。
こうした社会構造の変化は、都市部に「サラリーマン」層を出現させる。大正の半ば頃には、東京の丸の内一帯で朝出勤するサラリーマンたちの姿が目立つようになっていた。彼らは独自の生活スタイルを生み出す中産階級となり、都市部の文化を大いに発達させた。活動写真館やダンスホールなどの娯楽施設が広まり、カフェー、ビアホール、喫茶店など洋風の食事や飲み物を楽しめる場所も次々にできた。そういった場でビールを飲むサラリーマンが増え、ビール文化は都市部を中心に急激に広まった。この頃、ビールを飲む人々を指して「ビール党」という言葉が生まれた。
これに伴い、ビールの国内需要は急増する。第一次世界大戦開戦の1914(大正3)年には約24万186石(約4万3,233KL)だった全国のビール生産量は、大戦が終結した翌年の1919(大正8)年には約64万8,698石(約11万6,766KL)になり、5年間で約2.7倍も成長した。
ビール各社はキャッチフレーズに工夫をこらし、新聞広告やポスターをはじめとしたさまざまな広告を出した。その後もビール生産量は、年によって変動はあったが上昇を続け、1939(昭和14)年には約173万4,435石(約31万2,198KL)と戦前最高の生産量を記録した。
このように大正期に生まれた新しいビール文化は、第二次世界大戦時に統制が本格化するまで、大いに繁栄した。