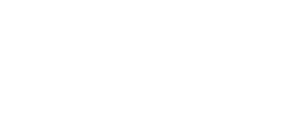横浜でスプリングバレー・ブルワリーを経営していたコープランドは、1875(明治8)年には醸造所の隣に
ビアガーデンを設けていた。横浜に寄港する外国船の船員たちでにぎわったという。
その後ビールのコップ売りや一杯売りなども出現したが、大規模なビール会社ができると、その宣伝も兼ねてビアホールが開設されるようになっていく。
1895(明治28)年頃に大阪にできた「ビール会」は、臨時営業のビアホールのようなもので、初めは夏場だけだったが、やがて年間を通して営業するようになった。1899(明治32)年12月には、中之島公園前の「アサヒ軒」が冬季の営業開始をうたった広告を出している。
そして1899(明治32)年、東京・新橋に
「恵比寿ビヤホール」がオープンし、大盛況となった。「ビヤホール」の名称は、日本在住の外国人のアドバイスで決まったといわれ、その人気にあやかり、東京に「ミルクホール」、「正宗ホール」なども登場した。客層はさまざまで、馬車で遠方から来る者もあった。中に入ると「車夫と紳士と相対し、職工と紳商と相ならび、フロックコートと兵服と相接して、共に泡だつビールを口にし、やがて飲み去って共に微笑する処」という状態で、「四民平等とも言うべき別天地」(『中央新聞』1899年9月4日付)だったようだ。
この成功を見て、東京市内や地方都市にもビアホールが次々と開店した。
日本のビアホールはドイツの「ビアハーレ」が手本となっているようだ。初期のビアホールでは、ビアハーレと同じように大根を切ったものをつまみとして出していたが、日本人の口には合わず不評だったのですぐにやめてしまったという。
正岡子規はその最後の作品となる『病牀六尺』で、「自分の見た事もないもので、一寸見たいと思ふ物」の一つに「ビヤホール」を挙げている。この原稿が雑誌『日本』に掲載されたのは1902(明治35)年5月のことである。病の床にあった子規のところにも、知人を通してビアホールの大盛況の様子が伝わっていたのだろう。