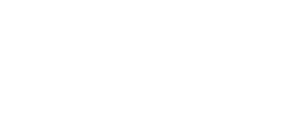江戸時代後期に入り、オランダ語を通じて西洋の文物を学ぶ蘭学が発達した。蘭学書にはたびたびビールが登場し、一部の日本人の間にビールの知識が広まり始める。
『解体新書』で知られる杉田玄白や前野良沢に学んだ
大槻玄沢は、1788(天明8)年に著した
『蘭説弁惑』の中で「『びいる』とて麦にて造りたる酒あり。食後に用るものにて飲食の消化をたすくるものといふ」と紹介している。玄沢がビールを飲んだ記録は残っていないが、出島のオランダ人とも交流があったことを考えると、実際に味わってみた可能性はある。シーボルトから医学と蘭学を学んだ
高野長英も『救荒二物考』で、オランダ人が「ビイル(酒名なり、少しく苦味ある者なり)」をつくるのにそばを使うことや、その製法について述べている。
なお、
『和蘭(おらんだ)問答』に「ビイル」、『蘭説弁惑』に「びいる」とあるのは、いずれもオランダ語の発音をそのまま表記したものだった。今日の「ビール」という名称の由来はオランダ語にあることが分かる。
蘭学者の間では、太陽暦の元旦を祝って会合を開き、料理をふるまう「阿蘭陀(おらんだ)正月」が慣例となっていた。出島でオランダ人が行っていた正月祝いを模したもので、1795(寛政7)年から40年余り続いた。オランダの料理は、『紅毛雑事書留』にその食卓の様子が記され、『長崎名勝図絵』でコース料理のメニューが記されるなど、江戸時代の書物にも紹介されている。こういった資料の中にはオランダ人が飲むアルコール類も紹介されていることから、「阿蘭陀正月」の食卓にもビールが並んだのではないだろうか。